3
新規事業は打率1割。出版はまだまだやれることがたくさんある
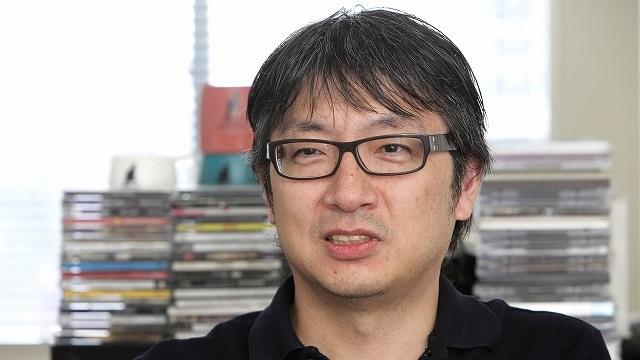
ソニー時代から新規事業を手がけ、社長になり11年。もちろん、すべてが順風満帆だったわけではない。さまざまな事業を手がける中には、手痛い失敗もたくさんあった。それでも続けた中で、さまざまなことが見えてきた。
「結局、新規事業の打率は一割です。大企業がやろうと中小企業がやろうと、10回スイングしてヒットは1本出るぐらいの確率なんですよね。
その感覚はソニー時代からありました。でも、ソニーという大会社のお金でやるのと自分の会社の身銭でやるのは違いますからね。失敗すると、昔よりずっとストレスがたまる(笑)。それほど大金を投資するわけではなくても、9回空振りするとさすがに焦ってきますし。
ただ確率的に言えば、1本ヒットを打つためには10回スイングしなきゃいけない。だから、いろいろな機会をアグレッシブに作っていかねばならない。そういう意味で、僕らは常に崖っぷちですよ。
そして広畑さんが新しいことをする時、特に重要視するのが「関係する登場人物」だという。
「上手くいかない時は『船頭多くして船山に上る』という例えの通りになるんです。大きさを問わず、どんな事業でも船頭が何人かいますよね。それぞれの役割分担がきっちりしていて、方向性とタイミングが合っている時、たいていの物事は正しい方向に動く。でも、優秀な能力を持っている人がたくさんいるから成功する、というわけでは決してない。みんなアクが強くてバラバラだったらダメ。メンバーがしっかりコミュニケーションを取り、コンセンサスを共有しながら役割を明確にし、都度修正を加えていく。それができないと、どんどんずれていってしまうんですよね」
そんなディスクユニオンの事業の中で、これからさらに注力していく分野が出版事業である。若年層を中心とした本離れと依然として続く出版不況、そして紙から電子書籍へのシフト。変革の時を迎えた出版業界において、彼らが果たそうとしている役割とは何なのか。
「いわゆる専門書は、まだまだ伸びる余地があると思っています。今、1日200タイトルもの新刊が出版されますので大手書店でも運ばれてきた新刊すべてが売場に並べられずに返本されるケースもあると聞いています。特に専門書は厳しい状況だと思います。ということは、それがきちんと一定期間店頭に置かれれば、来店客の目に触れる機会も増え、売れる可能性も高くなるし、出版社にとってもプラスになる。その想定のもと、まずは自店で「bookunion」という売場を作って音楽の専門書を拡販していこう、ということです。音楽の専門書であれば、ディスクユニオンのスタッフでも問題なく扱えますからね。


各出版社が電子書籍への取り組みに本腰を入れ始め、徐々に多くの書籍が電子化されてきていますが、当社の出版レーベル「DU BOOKS」の出版物の電子化はまだまだ後ですればいいと考えています。それは、音楽業界で音楽配信がどう進んできたを経験していますし、むしろ優良なコンテンツを生み出す土壌をしっかりと確立させたいと思っています。最初はわれわれの得意分野である音楽の専門書でトライして、どれぐらいできるかを見てみたい。そしてもっと他の分野の本も扱うことができる自信がつけば、さまざまなジャンルの展開も考えたいですね。ただしその際は、専門のスタッフが必要になりますが」
そして出版事業とともに、例えばブックカバー、ブックマーク、本棚といった読書用品の制作~販売にもさらに注力していく。

「あとはメンテナンス用品ですね。これが結構たくさんあるんですよ。例えば本の汚れを取るクリーナーとか、本棚や本を掃除するためのブックブラシとか。取り扱っている読書用品は全体で1000アイテムを超えました。珍しいところでは、ハヤカワ文庫専用のブックカバーなんていうのも販売しています(笑)。ハヤカワ文庫さんのサイズは若干縦が長いんですが、ぴったりのものを作りました。
これはもともと、レコード用品の販売がヒントになっています。レコードやCDを販売していると、いわゆる『ついで買い』でクリーナーやレコード袋などのアイテムが売れていくので、それを単独店でやってみたら、そこそこの需要があった。そこで、いわゆる用品を出版業界で当てはめてみると読書家に向けた「読書用品」だよね、ということになったんです。でも、ただ単に用品を扱うのではなく、マニア、愛好者のための気の利いたもの、という軸がないと、僕らがやる意味がない。そこが、決して見失ってはいけないポイントです」




何を扱おうと『マニアのための』という軸がしっかりと通っていること。それこそが、ディスクユニオンの展開する"ディープ"オーシャン戦略の大切なエッセンスだ。
「正直、出版も、紙の本は間違いなくシュリンクしていきます。でも、やり方次第ですよね。だって出版の市場規模は、音楽業界からしてみると音楽ソフトの3倍もあるし、出版業界より先にノンパッケージの洗礼を受けてきたので、『何言ってるの!? まだやれることはたくさんあるよ』です(笑)。時代の流れに対応して進化してさえいけば、必ず生き残ることができる。僕はそう信じています。」
(終わり)
※ 会社、役職、年齢など、記事内容は全て取材時のものです